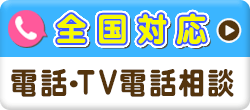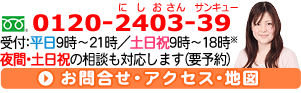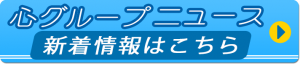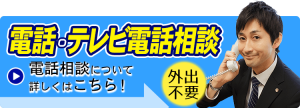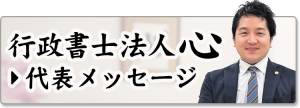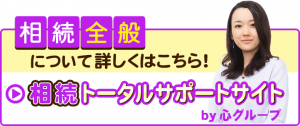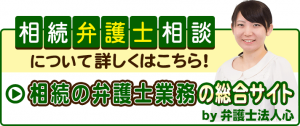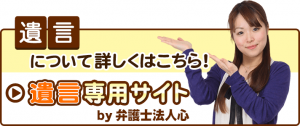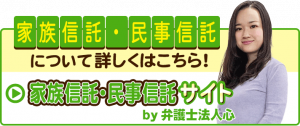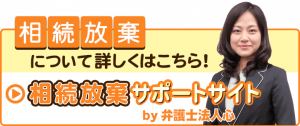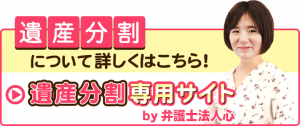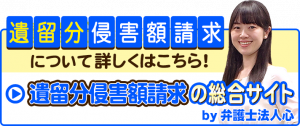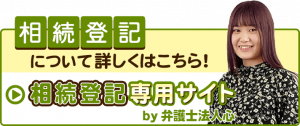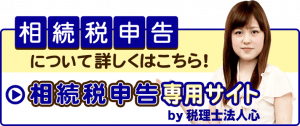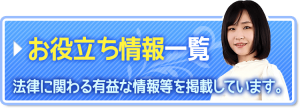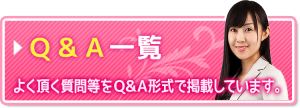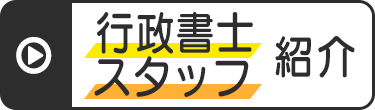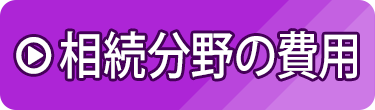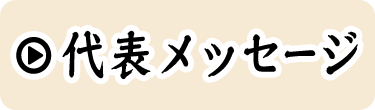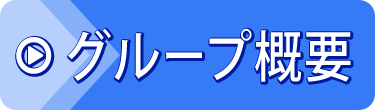相続手続きの必要事項に関するQ&A
- Q相続手続きでは何をする必要がありますか?
- Q相続人調査と相続財産調査では何をする必要がありますか?
- Q遺産分割では何が必要ですか?
- Q相続登記はどのような場合に必要ですか?
- Q相続税申告はどのような場合に必要ですか?
Q相続手続きでは何をする必要がありますか?
A
相続手続きで行う代表的なこととしては、次のものが挙げられます。
① 相続人調査
② 相続財産調査
③ 遺産分割協議
④ 相続登記
⑤ 相続税申告
「①相続人調査」と「②相続財産調査」は、多くの相続手続きの前提として行うべきことですので、一般的にはまずこの2つを行う必要があります。
その後、「③遺産分割協議」で作成した遺産分割協議書を用いて、「④相続登記」と「⑤相続税申告」を進めていくという流れになります。
Q相続人調査と相続財産調査では何をする必要がありますか?
A
⑴ 相続人調査
まず、行うべきことは、被相続人の相続人の確定です。
様々な相続手続きで必要となる遺産分割協議書を作成するためには、遺産分割を行う必要があります。
遺産分割はすべての相続人で行わないと、無効になってしまうため、相続人を確定させること重要な作業となります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集します。
代襲相続人がいる場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も収集する必要があります。
必要な戸籍謄本の収集が終わったら、法務局で法定相続情報一覧図を作成しておくと、その後の相続手続きの際に便利です。
⑵ 相続財産調査
相続財産調査は、地道にひとつずつ進める必要があります。
一般的には、現金、預貯金、不動産(土地、建物)、株式や投資信託、貴金属などの価値の高い動産を調査します。
相続税申告が必要であると考えられる場合、生命保険金も相続財産とみなされるので、調査が必要です。
貯金通帳の確認、銀行や証券会社への残高照会、固定資産税納税通知書の確認や不動産の登記事項証明書の取得、保険証書の確認などを行います。
また、相続財産はプラスの財産だけではありません。
ローンなどの借金や、保証債務などマイナスの負債も調べる必要があります。
財産調査の結果によっては、相続放棄や限定承認などの判断をすることもあります。
Q遺産分割では何が必要ですか?
A
相続人と相続財産の調査が完了したら、次はどの相続人がどの相続財産を取得するかを話し合って決めます。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、実務上は遺産分割協議書に相続人全員で署名押印をします。
押印には実印を用い、印鑑証明書も添付します。
Q相続登記はどのような場合に必要ですか?
A
相続財産に不動産が含まれている場合は、被相続人から相続人に名義変更をする相続登記を行う必要があります。
2024年4月からは相続登記が義務化されていますので、期限内に相続登記をする必要があります。
相続登記は、自己のために相続の開始があったこと、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法定相続分での登記が必要となります。
法定相続分での登記をした後に遺産分割をした場合、その日から3年以内に相続登記が必要です。
3年以内に遺産分割ができる場合は、遺産分割の後に1回相続登記をすれば問題ありません。
遺産分割協議が長引いている場合などにおいては、法定相続分での登記に代えて、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることもできます。
その後に遺産分割講義が完了したら、遺産分割の日から3年以内に相続登記をします。
正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料に処されることになります。
相続登記の際には、相続登記申請書のほか、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票(住所証明)、遺産分割協議書などを揃えて、管轄の法務局に提出します。
Q相続税申告はどのような場合に必要ですか?
A
相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合、基本的には相続税申告が必要になります。
生命保険金や死亡退職金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算においては相続財産とみなされますので、相続財産の評価額を計算する際には算入する必要があります。
基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人である場合は、3000万円 + 600万円 × 3 = 4800万円が基礎控除額になります。
原則として、相続財産がこの金額を超えると相続税申告、納付義務が発生します。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日(一般的には、被相続人がお亡くなりになられた日)の翌日から10か月です。
期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課されることがあります。
また、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを利用した場合、税額が大きく減り、納税額が0円になることもありますが、そのような場合でも申告が必要ですので注意が必要です。